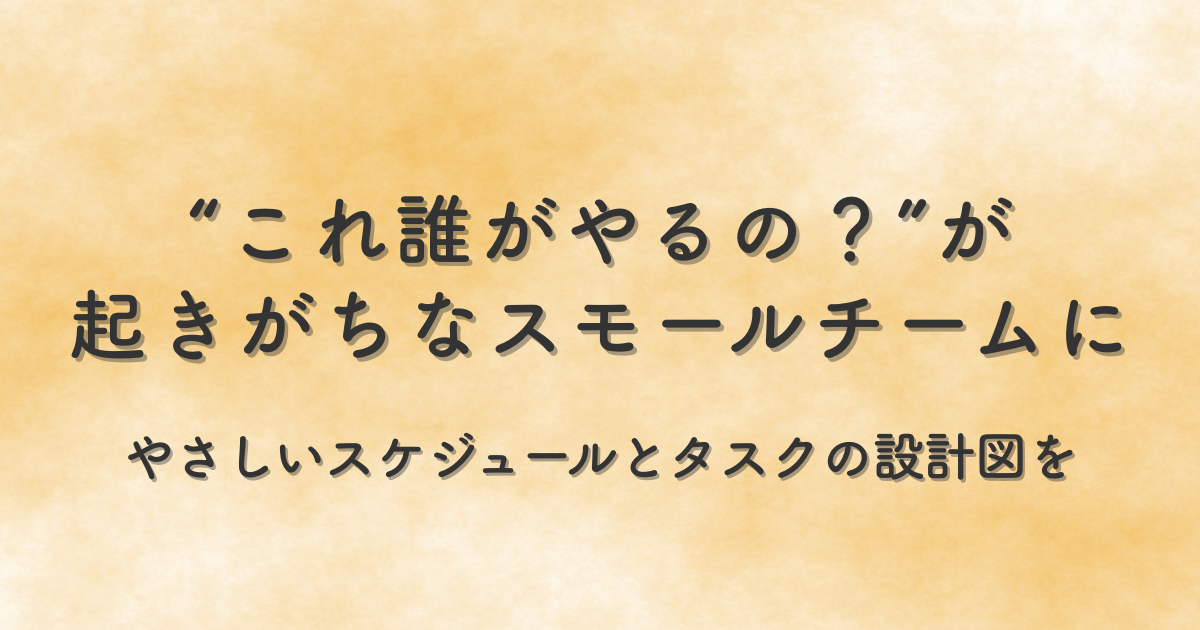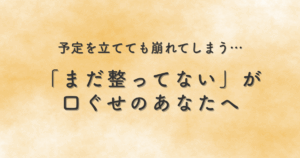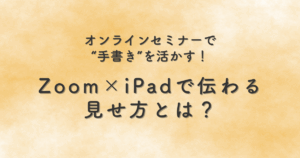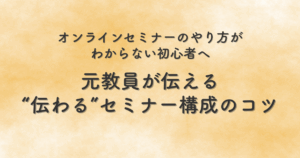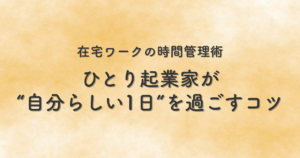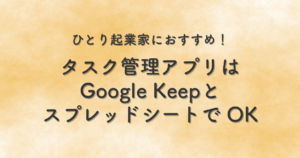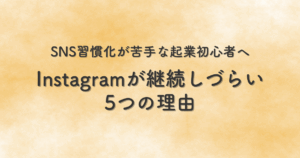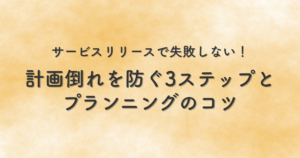スモールチームで動くとき、よくあるのが「結局あの作業、誰がやるの?」という状態。
特に元教員だった私の経験からすると、“責任感が強い人ほど、何でも自分で抱えがち”。
結果、気付いた人が率先してやって疲弊したり、チームが育たない…という問題が起こりがちです。
本記事では、そんなチームにありがちな「宙ぶらりんのタスク問題」への対処法や、小さなチームでも動きやすくなる“やさしいスケジュール設計図”の考え方をまとめました。
スモールチームにありがちな「宙ぶらりんの業務」

「気づいた人がやる」文化が根強い
スモールチームでは、「誰かがやってくれる」という暗黙の了解が生まれやすく、結果として“気づいた人”だけが動く構図になりがちです。
特に、教員のようなひとりで様々な業務をこなす職種の方、そして、これまで全ての業務をひとりでこなしてきたひとり起業家さんほど、つい人にお願いすることを忘れて自分でやってしまいます。
その結果、メンバーに任せる意識が育たないまま、リーダーだけが疲弊する状態になることも。
人数が少ないからこそ、見過ごされがちな問題です。
タスクの担当者が決まらないと進まない
誰がどの作業を担当するのかが曖昧だと、「まだ誰もやっていない」まま放置されてしまうリスクがあります。
たとえば、最初の会議で「これをやろう!」と決めたのに、次の会議で「あれってどうなったの?」と気づくケース。
結果、直前になってバタバタしてしまい、「チームはどこに向かうのか?」を見落とす要因にもなり得ます。
ですが、チームメンバーは悪気があるわけではなく、「自分の役割じゃないと思っていた」だけということも多いのです。
責任の所在が見えにくいチームでは、タスクも自然と流れていってしまいます。
「言わなくても分かる」幻想の怖さ
少人数のチームでは、「このくらい言わなくても伝わるだろう」と思いがち。
ですが、実際には“やってほしいこと”と“伝えたこと”には大きなズレがあるのが現実です。
言葉にして共有することの大切さを、あらためて意識する必要があります。
ちなみにこれは、プライベートの旅行でも同じです。
「誰が何をするか」が決まっていないと、当日バタバタしたり、やることが宙ぶらりんになったりしがちですよね
(「誰が予約してくれるのかな?私がやるって言った方がいいのかな?」と、やきもきしたことはないですか?)
旅行ですらそうなのですから、ビジネスならなおさら。
小さなチームであっても、明確な役割分担が必要なのです。
「やさしい設計図」とはどういうもの?

「無理のない流れ」で組まれているか?
スモールチームにおけるスケジュールやタスクの設計図は、「誰か一人に負担が偏らない流れ」であることが大切です。
リーダーが全部を把握・調整しようとすると、結局自分の首を絞めてしまいます。
そして、自分自身が動いてしまうことで全体が見えづらくなり、トラブルが起こっていても気が付かない…なんてことも。
少人数だからこそ、“できる人がやる”ではなく“やりやすい形で分担する”ことが重要。
無理なく進められる流れこそが、継続可能な設計図になります。
「誰が何をするか」が明確に見えるか?
「これ誰がやるんだっけ?」が起きないようにするには、役割と最終責任者を見える形で示すことが大切です。
「みんなで協力しよう」という空気感は良くても、それだけでは実際のタスクは回っていかないもの。
主に動かす人が一人明確になっているだけで、仕事は回りやすくなるのです。
役割が決まっていることで意見を言いやすくなったり、行動しやすくもなります。
「ふりかえり前提」で組み替えがしやすいか?
完璧なスケジュールを最初から作る必要はありません。
むしろ、やってみてから振り返って調整できる柔軟さの方がチームには必要です。
スモールチームの場合、状況が変わるスピードも早いため、“試してみてから整える”という姿勢が機能します。
「やりながら調整していく」前提で、仕組みを作ることがコツです。
スケジュール作成の3つのポイント

まず“全体像”を描く
スモールチームでスケジュールを作るときは、まず最終ゴールから逆算した全体像を描くことが重要です。
「今週何をやるか」から考え始めると、部分最適になりやすく、後からズレが出てきます。
ゴールとマイルストーンを先に決めてから細部を詰めると、計画がブレにくくなります。
全体を見通すことが、無理のない流れを作る第一歩です。
ざっくり→詳細にブレイクダウンする
最初から細かく決めすぎると、変更に対応できなくなることがあります。
まずはざっくりとした大枠を作り、進行に合わせて詳細を調整するのがスモールチームには合っています。
この「ざっくり→詳細」の流れがあると、メンバーの心理的負担も少なくなります。
余白のあるスケジュール設計が、柔軟性を保つポイントです。
共有方法と更新の仕組みをセットで決める
スケジュールは「作って終わり」ではなく、常に動く“生きた設計図”である必要があります。
そのためには、どこで共有するか(LINE?Googleカレンダー?Notion?)と、誰がいつ更新するかをあらかじめ決めておくのが効果的です。
こういった仕組みは、最初のうちはしっかり共有されていても後々放置されたり、気づけば何ヶ月も前から更新されていないということが起こることも
(年始には張り切って書いていた手帳を、だんだん開かなくなる…といった現象に似ていますね)。
これでは「形だけ」になってしまい意味がありません。
だからこそ、この「”共有の仕組み”の、積極的利用を促す役割の人」も必要になってきます。
共有と更新の仕組みがあれば、自然と情報が循環し、チーム全体が動きやすくなります。
一人一人が安心して仕事が進められる環境を

「全員が納得しているか」を確認する
スケジュールや役割分担が決まっていても、チーム全員が本当に納得しているかどうかは別の話です。
特に少人数のチームでは、遠慮や気遣いから本音が言えないこともあります。
特に、最近はオンライン上のやり取りだけで済ませ、スタッフ同士がざっくばらんに話ができる機会が少ないチームも多いと思います。
「これで本当に大丈夫?」と一度立ち止まる場をつくることが、後々のズレやストレスを防ぐのです。
一度決めたあとも更新できる柔軟性
決めたことにこだわりすぎると、状況が変わったときに無理が出てきます。
だからこそ、「途中で変更してもいい」前提の運用が大事。
一度決めたから変えてはいけない、ではなく、「よりよく進めるために変えていい」という雰囲気づくりが、安心感につながります。
相談できる空気感が、チームの動きをスムーズにするのです。
それぞれの視点を“翻訳”する役割の必要性
誰かが困っていたり、うまくいっていなかったりしても、それが全体に伝わらないことがよくあります。
そういう時に必要なのが、チーム内の“翻訳者”や”潤滑油”のような存在です。
困っている人の状況をくみ取り、リーダーや他のメンバーに伝えやすい形に整える人。
この“間に立つ人”がいるだけで、チームの摩擦はぐっと減ります。
スモールチームだからこそ、誰か一人が頑張るのではなく、チーム全体で支え合える仕組みを整えていきたいですね。